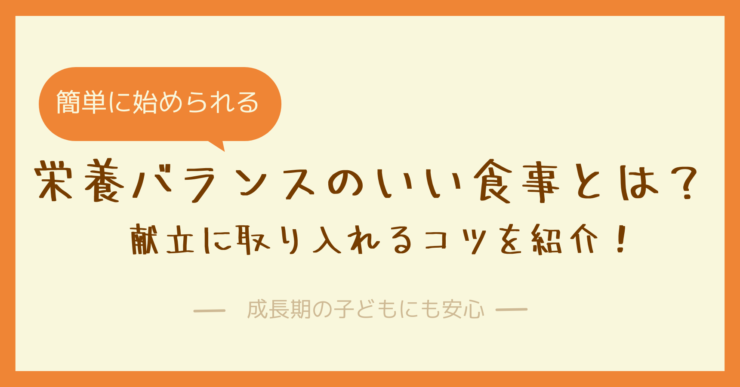【食生活改善入門ガイド】共働きでも無理なく続く!簡単にできる改善のコツを紹介

- 忙しくて食事の時間が不規則になりがちで、健康面が気になる
- 献立を考える余裕がなく、ついインスタント食品や外食に頼ってしまう
- 食生活を改善したいけれど、何から始めればいいのかわからない
栄養バランスの整った食生活は、家族全員の健康を支え、毎日を元気に過ごすための大切な要素です。しかし、共働きで忙しい家庭では、「何をどれだけ食べれば良いのか?」「どうすれば手軽に健康的な食事を用意できるのか?」と悩む人は多いです。
この記事では、子どもから高齢者まで役立つ、食生活の基本から実践的な方法まで詳しく紹介します。食事のバランスを整える方法や食品表示の見方、便利なレシピサイトや健康管理アプリの活用法など、無理なく実践できる食生活改善のコツなどを解説。日々の生活に取り入れやすい工夫を知り、家族みんなが笑顔で健康に過ごせる食卓を目指しましょう。
食生活改善のために知っておきたい基礎知識

食生活を見直すためには、基礎的な知識を身につけることが重要です。どれだけ忙しい生活を送っていても、栄養バランスを意識するだけで、家族全員の健康に大きな違いが生まれます。食生活改善を始めるうえで押さえておきたい以下の2点について紹介します。
- 主食・主菜・副菜のバランス
- 必要なエネルギー量の計算方法
主食・主菜・副菜のバランス

忙しい子育て中の共働き家庭では、毎日の食事を簡単に済ませがちです。ただし、健康を維持し、子どもの成長を支えるためには、主食・主菜・副菜を意識してバランスを整えることが重要です。少しの工夫で、無理なく栄養バランスの良い食事を準備できます。
主食(炭水化物)
- ご飯(特に玄米や雑穀米)やパン、麺類が中心。炭水化物は身体を動かすエネルギー源。
- 冷凍ご飯をストックしておくと、忙しい日でも温めるだけで用意が可能。
- 朝はトーストやシリアルを活用すると手軽に食べられる。
主菜(タンパク質)
- 肉や魚、卵、大豆製品(豆腐、納豆など)が体づくりに欠かせないタンパク質源。
- 鶏むね肉や鮭の切り身など、冷凍保存可能な食材を常備すると便利。
副菜(ビタミン・ミネラル)
- 野菜、きのこ、海藻類を活用して、ビタミンやミネラルを補う。
- 冷凍野菜を使うと、カットや洗う手間を省けます。スープや煮物にすぐ使えるので便利。
- 子どもが野菜を嫌がる場合は、カレーやハンバーグに細かく刻んで混ぜ込むと食べやすくなる。
赤(トマト、にんじん)、緑(ほうれん草、ブロッコリー)、黄色(パプリカ、とうもろこし)などカラフルな野菜を組み合わせ彩りを意識する自然と栄養価が高まり、見た目も食欲をそそります。
すべてを完璧に揃えるのは大変です。朝食は主食とフルーツだけ、昼はスープやサラダ中心にして、夕食で不足している栄養を補うといった形でもOKです。「1食で整えなきゃ」と思わず、1日の中でバランスを取るよう心がけましょう。
»栄養バランスのいい食事とは?簡単に献立に取り入れるコツを紹介!【成長期の子どもにも安心】
必要なエネルギー量の計算方法
健康的な食生活を送るためには、1日に必要なエネルギー量を知ることが重要です。共働き夫婦や育ち盛りのお子さんがいる家庭では、それぞれに適したエネルギー量を意識して、無理のない食事計画を立てることがポイントです。
- デスクワーク中心の共働き女性:約1800~2000kcal
- 外回りが多い共働き男性:約2200~2600kcal
- 活動的な成長期のお子さん:約2000~2500kcal
1日の食事は、朝食、昼食、夕食の3つに分けてエネルギーをバランスよく摂取することが大切です。それぞれの食事が1日のエネルギーの何割を占めるかを考えながら計画すると、自然と栄養が整いやすくなります。
- 朝食:1日のエネルギーの20~25%
- 昼食:1日のエネルギーの30~40%
- 夕食:1日のエネルギーの30~40%
例えば、1800kcalが1日の目安エネルギー量の女性の場合、
朝食:約400kcal(トースト+卵+ヨーグルト)
昼食:約600kcal(ご飯+魚の煮つけ+野菜炒め)
夕食:約700kcal(鍋料理+果物)
というような量が目安になります。
エネルギー量の目安を意識することで、栄養バランスを取りやすくなります。「細かく計算するのは面倒…」という場合でも、ざっくりした目安を知るだけで十分です。お子さんや夫婦それぞれの活動量や生活スタイルに合わせて、適切な量を取るよう心がけましょう。
食生活のよくある悩みと対処法

共働き家庭では、限られた時間の中で家族全員の健康を守る食事を準備するのが大変です。ここでは、よくある食生活の悩みとその対処法を以下の3つの視点から紹介します。
- 食べてもすぐにお腹が空く
- 野菜が苦手で量を食べられない
- 食事制限で栄養バランスが崩れてしまう
食べてもすぐにお腹が空く

食事をちゃんと摂ったのに、すぐにお腹が空いてしまうと感じる場合、食べる内容や食べ方が原因になっていることがあります。日々の食事に少しの工夫を取り入れるだけで、満腹感が長持ちし、間食の頻度を減らせます。
満腹感を長持ちさせるために意識するポイントは、次のとおりです。
- 食物繊維を意識して取る
- タンパク質をしっかり取る
- 低GI食品を選ぶ
- 水分補給を忘れない
- 脂質を適量摂取する
- 発酵食品を取り入れる
これらを意識して食事を工夫することで、食べ過ぎを防ぎながら、満足感のある食生活を実現できます。家族全員で取り組める簡単な方法なので、忙しい日々にもぜひ取り入れてみましょう。
野菜が苦手で量を食べられない

子どもが野菜を嫌がったり、忙しい共働き家庭で野菜が不足しがちだったりするのはよくある悩みです。ビタミンやミネラルを十分に摂らないと、体調や免疫力にも影響を与えかねません。野菜が苦手な人でも無理なく食べられる工夫は、以下のとおりです。
- 野菜を細かく切る・すりおろす
- 味付けや調理法を工夫する
- 見た目を楽しくする
- スムージーやジュースにする
- 凍野菜やレトルト商品を活用する
- 野菜をパンやお菓子にアレンジする
- 子どもと一緒に料理をする
- サラダに一工夫する
- 一品料理に野菜をたっぷり入れる
- 少量からスタートする
これらの工夫を取り入れれば、野菜が苦手な子どもや家族でも、少しずつ野菜を食べられるようになります。

間食としてスムージーやジュースにするのがおすすめ!砂糖の使い過ぎには注意して!
»子育て中の共働き夫婦におすすめな野菜宅配ランキング5選【失敗しない選び方を伝授】
食事制限で栄養バランスが崩れてしまう
ダイエットや健康管理で食事制限をすると、栄養バランスが崩れることがあります。特に糖質や脂質を極端に減らしたり、特定の食品に偏った食事を続けると、体調不良や免疫力の低下につながることもあります。バランスを保ちながら無理のない食事制限を行うために、次の点を意識しましょう。
- 極端に食品をカットしない
- 必要なタンパク質を確保する
- ビタミンやミネラルを意識的に摂る
- バランスの取れた食事を心がける
- 無理な制限を避ける
食品を極端に「抜く」食事制限は、体に負担をかけるだけでなく、リバウンドしやすくなってしまいます。糖質を完全に抜くのではなく、白米を玄米や雑穀米に変えるなど「置き換え」が効果的です。脂質はアボカドやオリーブオイル、ナッツなど良質な脂質を適量摂ることで、満足感を得られながら健康的に続けられます。
食事制限中でもタンパク質は特に重要です。筋肉や免疫力の維持には欠かせない栄養素なので、体重1kgあたり1~1.5gを目安に摂取することをおすすめします。鶏むね肉や魚、大豆製品など手軽に摂れるものを活用しましょう。
食生活改善のポイント
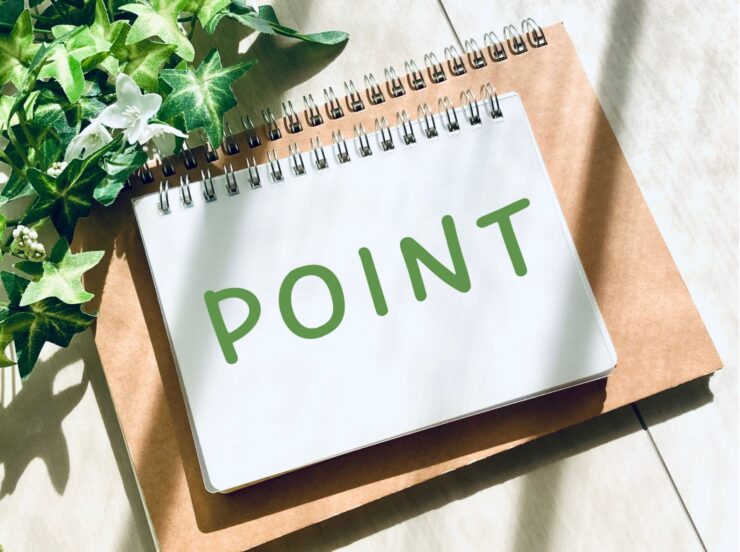
毎日の食事を少し意識するだけで、栄養バランスを整え、健康的な生活を送ることができます。無理なく続けられる食生活改善のポイントを以下の7つです。
- 朝食の重要性
- 食べる量と時間の管理
- 食品表示の見方と選び方
- インスタント食品・加工食品の影響
- 外食や間食の選び方
- 食事の記録をつけるメリット
- 食事の楽しみ方
朝食の重要性
朝食は、1日のエネルギー源として欠かせない食事です。特に育ち盛りのお子さんにとって、朝食を摂ることは学習能力や集中力の向上につながり、大人にとっても代謝の活性化や体調管理に重要な役割を果たします。朝食には下記のメリットがあります。
- 脳の働きを活性化する
- 体の代謝を促進する
- 空腹によるストレスを防ぐ
- 血糖値を安定させる
- 生活リズムを整える
- 過食や間食を防ぐ
朝食には、全粒穀物やタンパク質、果物などを組み合わせたバランスの良いメニューが理想です。忙しい朝でも、作り置きや手軽に食べられる食材を活用すれば無理なく続けられます。
食べる量と時間の管理
健康的な体を維持するためには、食事の間隔や食べる速さを意識することが大切です。規則正しい食事習慣を作ることで、体内リズムが整い、家族全員がより元気に過ごせるようになります。
食べる速さにも注意が必要です。早食いは満腹感を感じにくく、結果的に食べ過ぎにつながることがあります。ゆっくりと食事をすることで、無駄なカロリー摂取を防ぎ、消化吸収も良くなります。食べる量と時間について、以下のポイントを意識しましょう。
- 咀嚼を意識して、食べ物をよく噛む
- 食事中に水分を取る
- 決まった時間に食事を摂り、リズムを整える
- 無計画なスナックや間食を控える
- 間食をする場合は、ナッツやヨーグルトなど栄養価の高いものを選ぶ
- 夜遅い時間の食事は避け、消化に良いものを軽めに摂る
- 食事に集中し、無駄なカロリー摂取を避ける
- 食事量を時間帯に応じて調整する(朝と昼は多めに、夜は控えめに)
これらのポイントを意識することで、忙しい中でも食事の質を上げることができます。最初から完璧を目指す必要はありません。小さな習慣から取り入れていくことで、家族みんなが健康的な生活を送りやすくなるでしょう。
食品表示の見方と選び方

食品表示には、その食品に含まれる栄養素やカロリー、添加物などの情報が記載されています。食品表示を見るときのポイントは以下のとおりです。
- 栄養成分表示
1食分のカロリーや塩分量を確認し、1日の目安摂取量と比較する。塩分は1日6g未満が理想的。 - 原材料名の順番
使用量が多い順に記載されている。一番初めに砂糖や油脂が記載されている場合は注意。 - 食品添加物
保存料や着色料、甘味料が多い食品は避ける。子どもが食べる場合は特に無添加や保存料不使用のものがおすすめ。 - アレルギー情報
小麦、卵、乳製品など特定原材料を確認し、注意書きも見逃さない。
食品表示を確認すると、自分に合う食品や避けるべき食品を判断する力が身につきます。栄養バランスを考える際は、タンパク質や食物繊維の量をチェックすると健康的な選択につながります。食品を選ぶときは、次のポイントを意識するとよいでしょう。
- カロリーだけでなく、栄養バランスも意識する
低カロリー商品を選ぶ際も、タンパク質や食物繊維がしっかり含まれているか確認しましょう。 - 自然に近い食品を選ぶ
原材料が「○○のみ」や、少数の材料で構成されているものを選ぶと安心です。 - 加工食品には頼りすぎない
冷凍食品やインスタント食品は便利ですが、できるだけ手作りの食事を基本にすることで健康を守れます。
食品表示を確認する習慣をつけることで、家族の健康を守りやすくなります。最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると短時間で必要な情報を読み取れるようになります。
インスタント食品・加工食品の影響

インスタント食品や加工食品は手軽で便利ですが、栄養バランスが偏りがちになることがあります。忙しい共働き家庭にとって強い味方である一方で、摂りすぎると健康に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。インスタント食品・加工食品の影響の影響は以下のとおりです。
- 塩分や脂質が多く含まれていることが多い。
- 保存料や着色料などの食品添加物が多く含まれている場合がある。
- ビタミン、ミネラルなどの栄養素や食物繊維が不足しがち。
- 食べ慣れると「味が濃い食べ物」に偏り、家庭料理が物足りなく感じる。
インスタントラーメンに野菜や卵を加えるだけでも栄養バランスが大きく改善されます。調味料を全て使わず、量を減らすことで塩分を抑えることができます。「低塩分」や「低脂質」の商品を選ぶのも良い方法です。インスタント食品は毎日の食事ではなく、忙しい日の「サポート」として活用することを心がけましょう。
加工食品を選ぶ際には、添加物が少ないものや、自然な材料で作られている商品を選ぶと安心です。原材料や栄養表示をチェックする習慣をつけることで、より健康的な選択ができます。
外食や間食の選び方
外食や間食は忙しい毎日の中で便利な選択肢ですが、何を選ぶかで健康への影響が大きく変わります。子育て中の共働き家庭では、以下のように外食や間食を工夫することで、栄養バランスを整えながら楽しく取り入れることができます。
- 野菜が多めのメニューを選ぶ(サラダや副菜が付いた定食など)
- 揚げ物よりも焼き物・蒸し物を選ぶ
- 丼ものより、主菜と副菜が分かれたメニューを選ぶ
- 調味料はかけすぎず、量を調整する(ドレッシングやタレを半分にするなど)
- ナッツ、ヨーグルト、フルーツなど栄養価の高い間食を選ぶ
- スナック菓子は控えめにし、代わりにドライフルーツや全粒粉のクラッカーを取り入れる
- 間食のタイミングを昼食と夕食の間に決めて少量にする
- 飲み物は甘いジュースより、水や無糖のお茶を選ぶ
外食や間食は、選び方を意識することで健康的な食生活を保つこともできます。栄養バランスを考えた選択を心がけ、楽しみながら健康的な生活を続けましょう。
食事の記録をつけるメリット

毎日の食事内容を記録することは、健康的な食生活を実現するために非常に効果的です。特に忙しい共働き家庭では、自分や家族の食事内容を振り返る良い機会となり、改善点を見つけやすくなります。記録をつけることで得られるメリットは次のとおりです。
- 食事の内容を可視化できることで、栄養バランスの偏りに気づける
- 無意識に摂りすぎている食品や不足している栄養素を把握できる
- 健康目標(体重管理や栄養補給)を達成するための具体的な行動につながる
- 外食や間食の頻度がわかり、改善ポイントを明確にできる
- 記録を家族で共有することで、食生活を一緒に見直すきっかけを作れる
食事の記録は紙に書く方法だけでなく、スマートフォンの健康管理アプリを活用するのもおすすめです。写真を撮るだけで簡単に記録できるアプリもあり、忙しい日々でも手軽に取り組めます。
食事の楽しみ方

忙しい日々でも、食事は単なる栄養補給の場ではなく、家族とのコミュニケーションやリラックスの時間として楽しみたいものです。工夫次第で食事の時間をより充実したものに変えることができます。
- 家族全員で食卓を囲み、会話を楽しむ時間を作る
- 季節の食材を使い、旬を感じられるメニューを取り入れる
- 食事の見た目にこだわり、彩り豊かに盛り付ける
- 時には新しい料理や国のメニューに挑戦して、食卓に変化を加える
- 食べるスピードを意識して、ゆっくりと味わう時間を持つ
- 特別な日には簡単なデザートや飾り付けで、食卓を華やかにする
食事を楽しい時間にすることで、家族の絆も深まり、食べることへの意識もポジティブに変わります。特に子どもにとっては、「食事=楽しい時間」というイメージが健康的な食習慣の基盤となります。家族全員が笑顔になれる食卓を目指してみましょう。
【目的別】食生活改善のポイント

食生活を改善するといっても、目的によって適した食事の取り方は異なります。ダイエットをしたい方、運動習慣がある方、高齢の方など、それぞれに合った食事の工夫を取り入れることで、より効果的に健康を維持できます。
ここでは、目的別に食生活改善のポイントを紹介します。
- ダイエットをしている人
- スポーツや筋トレをしている人
- 高齢者
- 食生活改善に役立つツール
ダイエットをしている人

ダイエットを成功させるためには、無理なく続けられる食事管理が重要です。極端な食事制限ではなく、栄養バランスを意識した方法で、健康的に目標を達成しましょう。
- 栄養バランスを重視する
・単品ダイエットや特定の栄養素を抜く食事法はおすすめしません。炭水化物、タンパク質、脂質をバランスよく摂りつつ、全体のカロリーを管理することが大切です。
・1日のエネルギー消費量から10~20%程度のカロリーを減らすのが理想的です(例:1日2000kcal消費する場合、約1600~1800kcalに調整)。 - 炭水化物の種類を見直す
・炭水化物を抜くのではなく、低GI食品(玄米、全粒粉パン、さつまいもなど)を選ぶことで、血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪の蓄積を抑えます。 - タンパク質を意識する
・筋肉を維持し基礎代謝を高めるために、体重1kgあたり1.2~1.5gのタンパク質を摂取するのがおすすめです(例:体重50kgの人は60~75g)。
・卵、鶏むね肉、魚、大豆製品など、低脂肪で高タンパクの食品を取り入れましょう。 - 間食を計画的に取る
・空腹時間が長すぎると、次の食事で食べ過ぎてしまうことがあります。10時や15時に軽めの間食を取ることで、食欲をコントロールしやすくなります。
・ナッツ、無糖ヨーグルト、ゆで卵などが満足感を得られるおすすめの間食です。 - 調味料や油の使い方を工夫する
・塩分や砂糖を控えめにし、香辛料やハーブを活用することで、カロリーを抑えながら満足感のある味付けができます。
・炒め物の油を小さじ1(約4g)に抑えるだけでもカロリーカットにつながります。 - 満腹感を長持ちさせる食事法
・食物繊維が豊富な野菜や海藻類を先に食べることで、満腹感が持続しやすくなります(食べる順番を「野菜→タンパク質→炭水化物」にする)。
・よく噛んで食べることで、満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防げます。 - カロリーよりも「質」を意識する
・同じカロリーでも、栄養価の高い食品を選ぶことで健康を維持しながら減量が進みます。例えば、100kcalの菓子パンよりも、100kcal分のナッツやゆで卵のほうが栄養価が高く、満足感も得やすいです。
ダイエットを成功させるためには、極端なカロリー制限を避けることが大切です。食事量を大幅に減らすと、体はエネルギー不足を補おうとして代謝を落とし、痩せにくい状態になってしまいます。極端な食事制限はストレスやリバウンドの原因にもなりやすいため、無理のない範囲でカロリーを調整することが重要です。
食事の記録をつけると、摂取カロリーや栄養バランスを把握しやすくなり、改善点を見つけやすくなります。短期間で結果を求めるのではなく、ライフスタイルに合った無理のない食習慣を続けることが、健康的に体重を管理するポイントです。
スポーツや筋トレをしている人

運動の効果を最大限に引き出すためには、適切な栄養補給が欠かせません。特に筋トレをしている人は、筋肉の合成を促進し、効率よく回復するための食事が重要になります。バランスの取れた栄養摂取を意識し、トレーニングの成果をしっかり体に定着させましょう。
- タンパク質を意識的に摂る
・筋肉の合成を促すために、体重1kgあたり1.5~2gのタンパク質を摂取する(例:体重60kgの人は90~120g)。
・鶏むね肉、卵、魚、大豆製品、プロテインなどを活用し、1日を通してこまめに補給する。 - トレーニング後30分以内の栄養補給
・筋肉の回復を促すために、「タンパク質+炭水化物」の組み合わせを意識する。
・おすすめの例:プロテイン+バナナ、ツナおにぎり、卵かけご飯+味噌汁。 - 炭水化物の摂取を調整する
・運動前はエネルギー源として適量の炭水化物を摂る(オートミール、玄米、バナナなど)。
・運動後は筋肉の回復を助けるために、白米やパスタなどの吸収が早い炭水化物を摂取する。 - 良質な脂質を取り入れる
・持久力向上やホルモンバランスを整えるため、ナッツ、アボカド、オリーブオイル、青魚などの良質な脂質を適量摂取する。 - 水分補給を徹底する
・脱水はパフォーマンス低下につながるため、運動前・運動中・運動後にこまめに水を摂る。
・大量に汗をかく場合は、電解質(ナトリウム、カリウム)を含むスポーツドリンクや塩分補給も意識する。
トレーニングの前後の食事は特に重要です。運動前はエネルギー源となる炭水化物を中心に、消化の良い食事を摂りましょう。運動後30分以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、筋肉の回復と成長を助けるために、タンパク質と炭水化物をバランスよく摂取するのが理想的です。
筋トレやスポーツの効果を最大限に引き出すには、食事もトレーニングの一環として考えることが大切です。適切な栄養補給とトレーニングを組み合わせることで、より効率的に体を作り上げることができます。
高齢者
高齢者が健康を維持するためには、栄養バランスを整えるだけでなく、加齢に伴う体の変化を考慮した食事が必要です。筋肉量の減少や骨密度の低下、消化機能の衰えなどに対応した栄養補給を意識することで、健康的で活力ある生活をサポートできます。
- タンパク質をしっかり摂る
・加齢により筋肉量が減少する「サルコペニア(筋肉減少症)」を防ぐため、毎食にタンパク質を取り入れます。目安は体重1kgあたり1.2~1.5g(例:体重50kgなら60~75g)。
・鶏肉、魚、卵、大豆製品、乳製品が消化しやすくおすすめ。柔らかく調理した煮魚や豆腐入りスープなどを活用しましょう。 - カルシウムとビタミンDを意識する
・骨の健康を守るため、乳製品、小魚、海藻などカルシウムを多く含む食品を取り入れることが大切です。
・ビタミンD(きのこ類、青魚)と組み合わせると、カルシウムの吸収が効率的に行われます。日光浴でビタミンDの生成を促すことも効果的です。 - 炭水化物は質と量を調整する
・エネルギー源となるご飯やパン、芋類を適量摂取しますが、血糖値が気になる場合は、玄米や全粒粉パンなどを選ぶと良いでしょう。
・運動量が少なくなっている場合は、過剰な摂取を避けるよう調整が必要です。 - 食物繊維を増やす
・便秘を防ぐため、野菜、果物、海藻、きのこ類を積極的に摂取します。特に、腸内環境を整えるヨーグルトや発酵食品も効果的です。
・食べやすくするために、煮る・蒸すなどで柔らかく調理すると良いでしょう。 - 水分補給を意識する
・高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、1日1.5リットルを目安に水分を補給します。水やお茶、スープ、果物(スイカ、オレンジなど)から摂取するのも効果的です。
高齢者が食事だけで十分な栄養を摂れない場合、プロテインや育児用ミルクなどの補助食品を取り入れることで、栄養不足を効率的に補えます。ただし、補助食品に頼りすぎるのではなく、基本はバランスの取れた食事をベースにすることが重要です。医師や栄養士に相談し、自身に合ったものを選ぶことも大切です。
加齢に伴い体の変化が起こる中で、高齢者が健康的な生活を送るためには、日々の食事が大きな役割を果たします。適切な栄養補給とともに、食べる楽しみを大切にした食事作りを心がけましょう。
食生活改善に役立つツール

食生活を見直したいと思っても、「何をどう改善すればいいのかわからない」「毎日の食事管理が大変」と感じることもあるでしょう。ここでは、手軽に使えて継続しやすい3つのツールを紹介します。
- 健康管理アプリ
- レシピサイト
- 専門家によるアドバイス
健康管理アプリ
食生活を改善するには、現在の食事や栄養バランスを把握することが大切です。忙しい共働き家庭では、スマホの健康管理アプリを活用することで、簡単に食生活を記録・管理することができます。健康管理アプリを活用するメリットは以下のとおりです。
- 栄養バランスの可視化
- 目標設定と進捗の確認
- 食事の記録が簡単
- 健康習慣の継続をサポート
以下のアプリを活用することで、摂取カロリーや栄養素の偏りを把握しやすくなり、食生活の改善に役立ちます。さらに、目標を設定して進捗を可視化できるので、モチベーションを保ちながら続けやすくなるのも大きな魅力です。
- MyFitnessPal(マイフィットネスパル)
- あすけん
- Fitbit(フィットビット)
- カロミル
健康管理アプリを上手に活用すれば、日々の食生活を効率的に記録し、改善点を見つけるのが簡単になります。まずは1つアプリをダウンロードして試してみることで、健康的な食生活をサポートする良い習慣をスタートさせましょう。
レシピサイト

忙しい日々の中で、健康的でバランスの良い食事を作るには、手軽に使えるレシピサイトを活用するのがおすすめです。レシピサイトを上手に利用すれば、時短で作れるメニューや冷蔵庫の余り物を活用した料理など、日々の献立作りがぐっと楽になります。レシピサイトを活用するメリットは以下のとおりです。
- 簡単で時短できるメニューを見つけられる
- 栄養バランスを意識した献立が簡単に作れる
- 家族の好みに合わせたアレンジが可能
レシピサイトは、目的や状況に応じた検索機能が充実しているため、短時間で作れる時短料理や、健康的な低カロリーメニューを見つけるのに最適です。家族の「好み」や「栄養の偏り」に対応したレシピを検索すれば、より満足度の高い食卓を実現できます。
- クラシル
- DELISH KITCHEN
- E・レシピ
- Cookpad(クックパッド)
- オレンジページnet
レシピサイトを使えば、毎日の食事作りが効率的になるだけでなく、家族の健康を意識したバランスの取れた料理を無理なく準備できます。
専門家によるアドバイス

食生活を改善する上で、栄養士や管理栄養士などの専門家にアドバイスをもらうことは、非常に有効です。自分や家族の食事内容や健康状態に合った具体的なアドバイスを得ることで、効果的に目標を達成できる可能性が高まります。専門家に相談するメリットは以下の4つです。
- 自分に必要な栄養素やカロリー量を具体的に知ることができる
- 偏りがちな食事の改善方法を提案してもらえる
- 家族全員の健康を考慮した献立や調理法をアドバイスしてもらえる
- 持病やアレルギーがある場合でも安心して取り入れられる食事内容を教えてもらえる
栄養士に相談する方法としては、地域の保健センターや病院で実施されている栄養相談、オンラインで利用できる食事相談サービスなどがあります。最近では、スマートフォンのアプリを通じて専門家とチャットやビデオ通話で相談できるサービスも増えています。
- LINEヘルスケア
- あすけんプレミアムプラン
- オンライン栄養相談サービス(NutriSupportなど)
専門家のアドバイスは、正しい知識に基づいて実践的な解決策を教えてくれるため、短期間での食生活改善にもつながります。一度相談することで、今後の生活に役立つ知識を得られるでしょう。
食生活改善で家族の健康と笑顔を守ろう

食生活を改善するためには、栄養バランスを意識しながら、無理なく続けられる工夫を取り入れることが大切です。日々の食事に少しの工夫を加えるだけで、家族全員が健康的な生活を送れるようになります。
忙しい共働き家庭では、健康管理アプリやレシピサイトを活用したり、時には専門家のアドバイスを取り入れることで、より効率的に食生活を整えることができます。インスタント食品や間食の選び方、食品表示の見方を工夫するだけでも、食生活は大きく改善されるでしょう。
重要なのは、完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ始めることです。無理のない範囲で、自分たちのライフスタイルに合った方法を取り入れながら、家族みんなが笑顔で食卓を囲める時間を大切にしていきましょう。
「オイシックス」は、厳選された食材やミールキットを自宅に届ける、年会費・会員費無料の食品宅配サービスです。
毎週1500種類以上の安心・安全な商品が揃い、生産者が自分の子どもにも安心して食べさせられる品質です。
15分程度で調理ができるミールキットや、1週間分の食材とレシピがセットになったコースもあり、健康と美味しさを両立させた便利な食事を簡単に楽しめます。
オイシックス以外のサービスが知りたい方はこちらの記事もチェック!
»子育て中の共働き夫婦におすすめの食材宅配を徹底比較!【失敗しない選び方を解説】
»子育て中の共働き夫婦におすすめな野菜宅配ランキング5選【失敗しない選び方を伝授】