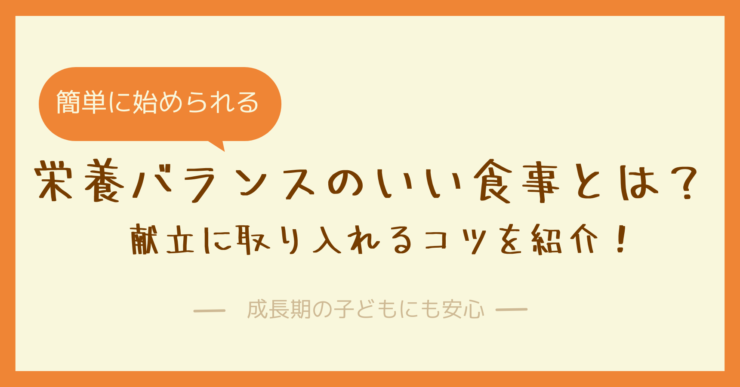【1日の塩分摂取量】大人・子どもの理想は?知らないと危険なリスクと減塩の工夫

- 1日にどれくらいの塩分を摂るのが理想なのか分からない
- 子どもの食事の塩分が気になるけれど、どう調整すればいいか分からない
- 外食や加工食品が多く、塩分を減らすのが難しい
塩分は体に必要な栄養素ですが、摂りすぎると高血圧や生活習慣病のリスクが高まります。特に子どもは大人と比べて適切な塩分摂取量が少なく、味覚が発達する時期でもあるため、薄味に慣れさせることが大切です。
この記事では、 1日に摂るべき塩分の目安や、家族みんなで無理なく減塩できる方法を紹介します。毎日の食事に少し工夫を加えるだけで、美味しく減塩しながら健康的な食生活を続けることができます。 今日からできる簡単なポイントを押さえて、塩分と上手に付き合いましょう!
1日の塩分摂取量の目安

健康を維持するためには、1日に摂取する塩分量を適切に管理することが重要です。目安となる塩分摂取量は、年齢や健康状態によって異なります。
1日の塩分摂取量の目安について、以下の3つの場合について紹介します。
- 成人
- 高血圧
- 子ども
成人
塩分の摂りすぎは高血圧や生活習慣病のリスクを高めるため、日々の食事で適量を意識することが大切です。特に、日本人は平均で1日約10gの塩分を摂取しており、推奨量を上回っているのが現状です。
健康を維持するための1日の塩分摂取量の目安は、以下のとおりです。
- 成人男性:7.5g未満
- 成人女性:6.5g未満
» 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より
日々の食事でこの基準を意識することで、血圧の上昇を防ぎ、将来的な健康リスクを軽減できます。特に外食や加工食品をよく利用する人は、塩分を摂りすぎやすいため注意が必要です。
妊娠中の女性は体調や個人差を考慮し、医師と相談しながら適切な塩分管理を行うことが望ましいでしょう。
高血圧

高血圧の人は塩分の摂取をより厳しく管理する必要があります。過剰な塩分は血圧を上昇させ、心血管疾患や脳卒中のリスクを高めるため、日々の食事で意識的に減塩を心がけましょう。
日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」では、 高血圧の人の1日の塩分摂取量の目安は6g未満とされています。健康な成人よりも厳しく設定されており、特に塩分の多い食品や濃い味付けに注意することが大切です。
塩分を控えることで、血圧を下げる効果が期待できるだけでなく、腎臓や心臓への負担も軽減できます。高血圧の改善や予防のためにも、日々の食事で無理なく減塩を続けることを意識しましょう。
子ども

子どもの塩分摂取量は年齢によって適切な基準が異なります。幼い頃から塩分を摂りすぎると高血圧のリスクが高まり、将来的な生活習慣病につながる可能性があります。成長に必要な栄養を確保しながら、塩分を適量に抑えることが大切です。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」による1日の塩分摂取量の目安は、以下のとおりです。
- 1~2歳:3.0g未満
- 3~5歳:3.5g未満
- 6~7歳:4.5g未満
- 8~9歳:5.0g未満
- 10~11歳:6.0g未満
特に加工食品やスナック菓子、外食の頻度が多いと、知らないうちに塩分を摂りすぎることがあります。子どもの健康を守るために、薄味に慣れさせる、だしや食材のうま味を活用するなど、日々の食事で工夫することが大切です。
日本人が1日に摂取する塩分量

日本人の塩分摂取量は、目標値よりも多くなりがちです。食文化や食習慣の影響で、知らないうちに塩分を摂りすぎていることも少なくありません。
ここでは、日本人の1日の塩分摂取量について、以下の2つの視点から紹介します。
- 年代別
- 地域別
年代別

日本人の塩分摂取量は年代によって差があり、中高年でピークを迎え、その後やや減少する傾向があります。厚生労働省の「令和五年度 国民健康・栄養調査」による年代別の1日あたりの平均塩分摂取量は以下のとおりです。
- 20代:男性 10.4g / 女性 8.3g
- 30代:男性 10.6g / 女性 8.1g
- 40代:男性 10.6g / 女性 8.9g
- 50代:男性 10.3g / 女性 8.9g
- 60代:男性 11.1g / 女性 9.5g
- 70歳以上:男性 10.7g / 女性 9.4g
若い世代は外食や加工食品の利用が多いため、塩分摂取量が高い傾向があります。一方で、中高年になると食事の味付けが濃くなり、塩分摂取量がさらに増加します。しかし、 70歳以上ではやや減少する傾向が見られます。
全年代で厚生労働省の推奨する摂取基準(男性9g未満・女性7g未満)を超えており、 特に60代以上は塩分摂取量が高く、高血圧や生活習慣病のリスクが高まるため、意識的な減塩が重要です。
地域別
日本人の塩分摂取量は地域によって差があることが分かっています。特に、寒冷地域や発酵食品が多い地域では、塩分摂取量が高くなる傾向があります。
厚生労働省の調査によると、東日本や北日本の地域では塩分摂取量が多く、西日本では比較的少ないという結果が出ています。これは、地域ごとの食文化や気候が影響しています。
- 東北地方や北陸地方:味噌や漬物、魚の干物などの発酵食品を多く食べるため、塩分摂取量が高め
- 関東地方:醤油を使った濃い味付けの料理が多く、塩分摂取量がやや多め
- 関西地方や九州地方:薄味の出汁を使った料理が多く、全国平均より塩分摂取量が少なめ
このように、地域の食文化によって塩分摂取量には違いがあるため、住んでいる地域の食習慣を意識しながら、減塩を心がけることが大切です。
塩分を過剰に摂取したときのリスク

塩分を摂りすぎると、健康にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。 体内のナトリウムバランスが崩れることで、生活習慣病や臓器への負担が増える原因になることも。
ここでは、塩分を過剰に摂取したときに起こりやすいリスクについて、以下の3つを紹介します。
- 高血圧と心血管疾患のリスク
- 腎臓への負担
- 骨粗鬆症のリスク
高血圧と心血管疾患のリスク
塩分を摂りすぎると、血液中のナトリウム濃度が上昇し、体が水分をため込もうとするため、血液量が増えて血圧が上がりやすくなります。これが慢性的に続くと高血圧になり、血管に負担がかかることで心血管疾患のリスクが高まるため注意が必要です。
高血圧が続くと、以下のような疾患を引き起こす可能性があります。
- 動脈硬化:血管の弾力が失われ、血流が悪化する
- 心筋梗塞:心臓の血管が詰まり、血流が途絶えることで心筋が壊死する
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血):脳の血管が詰まる、または破れることで意識障害や麻痺などの重い後遺症が残る
特に動脈硬化が進行すると血管がもろくなり、血圧の上昇とともに破れやすくなるため、脳卒中や心筋梗塞のリスクが一層高まります。さらに、高血圧は初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに血管へのダメージが進行し、ある日突然重大な病気を引き起こすこともあります。
塩分の摂取量を適切に管理することで、血圧の安定だけでなく、心血管疾患のリスクも低減できるため、日頃から食生活に気をつけることが大切です。
腎臓への負担

塩分を摂りすぎると、腎臓に大きな負担がかかります。腎臓は体内の余分な塩分(ナトリウム)を尿として排出する役割を持っていますが、過剰な塩分を処理し続けることで、腎機能が低下する可能性があります。
塩分の過剰摂取による腎臓への影響は、以下のとおりです。
- 腎臓の血流が悪化する:塩分の摂りすぎで血圧が上昇し、腎臓の細い血管に負担がかかる
- 慢性腎臓病(CKD)のリスクが高まる:腎機能が低下し、老廃物や余分な水分を排出しにくくなる
- むくみや倦怠感が現れる:体内に余分な水分が溜まりやすくなり、体調不良を引き起こす
- 腎不全に進行する可能性がある:腎機能がさらに低下すると、最終的に透析治療が必要になることも
塩分を適量に抑えることで、腎臓の負担を軽減し、健康な状態を維持することが重要です。
骨粗鬆症のリスク

塩分を摂りすぎると、体内のカルシウムが排出されやすくなり、骨がもろくなることが知られています。これが続くと、骨密度の低下や骨折のリスク増加につながるため注意が必要です。
特に、女性や高齢者は骨密度が低下しやすく、骨粗鬆症のリスクが高まるため、日頃の塩分管理が重要になります。
塩分の過剰摂取による骨への影響は、以下のとおりです。
- カルシウムの排出が促進される:ナトリウムとともに尿中へ排出され、体内のカルシウム量が減少する
- 骨密度の低下につながる:骨からカルシウムが溶け出し、骨がスカスカになる
- 骨折のリスクが高まる:骨がもろくなり、転倒などの衝撃で骨折しやすくなる
- 成長期の子どもにも影響を与える:十分なカルシウムが確保できないと、骨の成長が妨げられる
閉経後の女性はホルモンバランスの変化で骨密度が低下しやすく、骨粗鬆症のリスクがさらに高まるとされています。さらに、成長期の子どもも塩分の摂りすぎによって骨の発育に悪影響を受ける可能性があるため、家族全体で塩分管理を意識することが大切です。
骨の健康を守るためには、塩分を控えるとともに、カルシウムやビタミンDを意識して摂取することが重要です。
1日の塩分摂取量をコントロールする方法

塩分を摂りすぎないためには、日々の食事で意識的にコントロールすることが大切です。特に、外食や加工食品が多いと、気づかないうちに塩分過多になりやすいため、調味料の使い方や食材の選び方を工夫することがポイントです。
塩分を控えながら美味しく食事を楽しむための具体的な方法は、以下のとおりです。
- 減塩調味料を活用する
- 香辛料やハーブを活用する
- カリウムを増やす
- 食物繊維を積極的に摂る
- 具だくさんの汁物を作る
- 麺類の汁を残す
減塩調味料を活用する
塩分を控えながら美味しく食事を楽しむためには、 減塩調味料を上手に活用することが効果的 です。通常の調味料と比べてナトリウム量が少なく、塩味を抑えながらも風味を楽しめるものが多くあります。
代表的な減塩調味料の種類は、以下の4つです。
- 減塩しょうゆ
- 減塩味噌
- 減塩だし・つゆ
- 減塩塩・塩分カットの食塩
減塩調味料を選ぶ際は、「減塩」「低ナトリウム」「食塩○%カット」などの表示をチェックするのがポイントです。ただし、使いすぎると結局塩分過多になるため、適量を守ることが大切です。

減塩調味料を利用すれば、 普段の食事の味を大きく変えずに、無理なく減塩できますね!
香辛料やハーブを活用する

塩分を控えつつ美味しく食事を楽しむために、香辛料やハーブを活用するのが効果的です。香りや辛み、酸味を加えることで、塩味が少なくても満足感を得られるようになります。
塩分控えめでも風味を引き立てるおすすめの香辛料やハーブは、以下のとおりです。
ピリッとした刺激でアクセントを加えるもの
- こしょう:どんな料理にも合い、辛みと香りをプラス
- 山椒:和食との相性が良く、爽やかな辛みが特徴
- 唐辛子:少量でも味が引き締まり、減塩しやすい
- カレー粉:スパイスが複数ブレンドされており、コクと風味をプラス
酸味を加えてさっぱりさせるもの
- レモン・ライム・ゆず:魚料理や揚げ物に加えると、味が引き締まる
- お酢:ドレッシングや炒め物に加えると深みが出る
- トマト・トマトペースト:酸味と甘みがあり、煮込み料理のコクをアップ
香りで満足感をアップさせるもの
- にんにく・生姜:炒め物やスープに加えると、風味が増して塩分控えめでも美味しい
- ごま・ナッツ:コクと香ばしさをプラス
- セロリ・パクチー:独特の風味で、サラダやスープのアクセントに
ハーブを活用して味に深みを出すもの
- バジル・ローズマリー・オレガノ:洋風料理に適し、香りで満足感をアップ
- タイム・セージ:肉や魚の臭みを抑えつつ、風味豊かに
- ディル・フェンネル:魚料理やマリネに使うと、爽やかな香りが広がる
これらの香辛料やハーブを料理の仕上げに加えることで、塩分を減らしても物足りなさを感じにくくなります。

だしなど食材のうまみと組み合わせるのがおすすめです!
香辛料やハーブを上手に活用し、減塩しながらも豊かな味わいを楽しむ工夫をしてみましょう。
カリウムを増やす
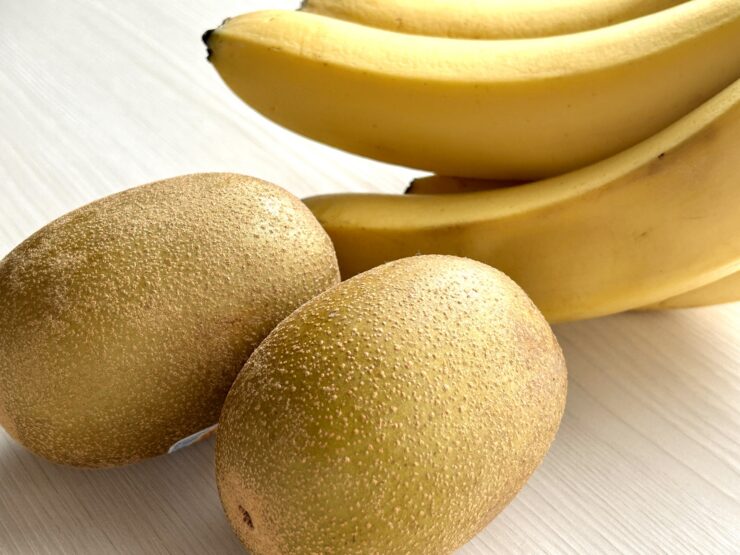
カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分)を排出し、血圧を下げる働きがあるため、減塩対策として積極的に摂取したい栄養素です。特に塩分の摂りすぎが気になる人や、高血圧の予防・改善をしたい人にとって、カリウムを含む食品を意識して摂ることはとても重要です。
カリウムを多く含む食品は、以下のとおりです。
- 野菜類:ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、じゃがいも、かぼちゃ、里芋
- 果物類:バナナ、キウイ、みかん、アボカド、メロン、干し柿
- 豆類・海藻類:納豆、大豆、ひじき、わかめ、昆布、もずく
- 乳製品・ナッツ類:ヨーグルト、牛乳、チーズ、アーモンド、ピスタチオ
カリウムは水に溶けやすい性質があるため、調理法にも工夫が必要です。茹でるとカリウムが流出しやすいため、スープや味噌汁など汁ごと食べられる料理にすると効率よく摂取できます。 生で食べられる果物やサラダも、カリウムを逃さず摂る方法のひとつです。
腎臓の機能が低下している人は、カリウムの排出が難しくなることがあり、体内にカリウムが過剰に蓄積すると「高カリウム血症」を引き起こす可能性があります。腎臓に疾患がある人は、医師と相談しながらカリウムの摂取量を調整することが大切です。
カリウムを意識的に摂ることで、塩分の排出を促し、血圧のコントロールにも役立つため、日々の食生活に取り入れるようにしましょう。
食物繊維を積極的に摂る

食物繊維には体内の余分なナトリウム(塩分)を吸着し、排出を促す働きがあります。塩分を摂りすぎたときや、日頃から減塩を意識したい場合には、食物繊維を積極的に摂ることが効果的です。
食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があり、どちらも塩分の排出に役立ちます。
水溶性食物繊維の働き
- 体内の余分なナトリウムを吸着し、便とともに排出する
- 腸内環境を整え、血圧の安定に貢献する
水溶性食物繊維を多く含む食品
- 海藻類:わかめ、ひじき、昆布、もずく
- 果物類:バナナ、りんご、みかん、柑橘類
- 豆類:納豆、大豆、オクラ
不溶性食物繊維の働き
- 腸の動きを活発にし、老廃物とともに塩分を排出しやすくする
- 腹持ちを良くし、食べすぎを防ぐ
不溶性食物繊維を多く含む食品
- 野菜類:ごぼう、キャベツ、ブロッコリー、にんじん
- きのこ類:しいたけ、しめじ、えのき、エリンギ
- 穀物類:玄米、雑穀、全粒粉パン
食物繊維はさまざまな食品からバランスよく摂ることが大切です。海藻や野菜、果物を日常的に取り入れることで、自然に塩分の排出をサポートできます。

腸内環境の改善や血糖値の安定にも役立つので、積極的に接種しましょう!
具だくさんの汁物を作る

減塩を意識しながら美味しく食事を楽しむために、具だくさんの汁物を作ることが効果的です。汁の量を減らし、野菜やきのこ、豆類などの具材を増やすことで、塩分を抑えつつ満足感のある一杯になります。
具たくさんの汁物が減塩に役立つ理由は以下のとおりです。
- 汁の量が少なくなることで、摂取する塩分を抑えられる
- 野菜やきのこ、豆類のうま味が活きるため、少ない調味料でも美味しく仕上がる
- カリウムや食物繊維が豊富な食材を使うことで、体内の余分な塩分を排出しやすくなる
おすすめの具材には、キャベツ、大根、小松菜などの野菜、しいたけやまいたけなどのきのこ類、豆腐や納豆などの豆類、わかめや昆布などの海藻があります。これらを活用すると、栄養価が高まり、うま味も増します。
減塩のコツとして、出汁をしっかり活用し、味噌や醤油の量を控えめにすることがポイント です。調味料は食べる直前に加えると、少量でも味をしっかり感じられます。
麺類の汁を残す
ラーメンやうどん、そばなどの麺類は、汁に多くの塩分が含まれているため、減塩を意識するなら汁を残すことが効果的です。
ラーメン1杯のスープをすべて飲むと約5〜6gの塩分 を摂取することになりますが、 汁を半分残せば約2〜3g、ほとんど残せば1g以下に抑えることが可能 です。
麺類の塩分を抑える工夫として、以下の方法もおすすめです。
- スープはなるべく少しずつ飲み、全部飲み干さないようにする
- 味の濃い汁の場合は、お湯やだしを少し加えて薄める
- 麺をすすった後、汁をなるべく切って食べる
トッピングに野菜や海藻、ゆで卵などを加えると、栄養バランスも向上し、満足感もアップ します。外食やインスタント麺を食べる際も、汁を残すだけで手軽に減塩できるため、意識してみましょう。
食品に含まれる塩分量

日常的に口にする食品には、思っている以上に多くの塩分が含まれていることがあります。特に加工食品や調味料は塩分が高いため、減塩を意識する場合は選び方に注意が必要です。
食品に含まれる塩分量の目安を、以下の3つの項目について紹介します。
- 調味料類
- 加工食品
- 主食・おかず
調味料類
調味料は料理の味を引き立てるために欠かせませんが、 知らないうちに塩分を多く摂ってしまう原因になることがあります。特に、しょうゆや味噌などの和風調味料は塩分が高いため、使い方に注意が必要です。
主な調味料に含まれる塩分量の目安(大さじ1あたり)は以下のとおりです。
- しょうゆ:約2.6g
- 味噌:約1.5g
- 中濃ソース:約1.2g
- ケチャップ:約0.5g
- マヨネーズ:約0.3g

だしの素やコンソメ、めんつゆなどにも塩分が含まれているので、使いすぎには注意しましょう!
加工食品

加工食品には、 保存性や風味を高めるために多くの塩分が含まれていることが多く、無意識のうちに塩分を摂りすぎる原因になります。ハムやソーセージ、漬物、インスタント食品などは塩分が高めなので、摂取量に注意が必要です。
主な加工食品に含まれる塩分量の目安(1食あたり)は以下のとおりです。
- ハム(1枚):約0.5〜0.8g
- ベーコン(1枚):約0.7〜1.0g
- ちくわ(1本):約1.0g
- 梅干し(1個):約2.0g
- インスタントラーメン(スープ込み):約5.5〜6.0g
- カップ焼きそば:約4.5〜5.5g
- レトルトカレー(1袋):約2.5g
加工食品は手軽で便利ですが、頻繁に食べると塩分過多になりやすいため、選び方や食べ方を工夫して上手に付き合いましょう。
主食・おかず
毎日の食事で摂取する主食やおかずには、意外と多くの塩分が含まれています。 特に加工食品や味付けの濃い料理は、知らないうちに塩分を摂りすぎる原因になります。
主食・おかずに含まれる塩分量の例は以下のとおりです。
- ご飯(白米・玄米など):ほぼ0g(塩分なし)
- 食パン(6枚切り1枚):約0.8g
- うどん(1杯・つゆ含む):約5.5g
- ラーメン(1杯・スープ含む):約6~7g
- 焼き魚(塩サバ1切れ):約2.0g
- 味噌汁(1杯):約1.5~2.0g
- 漬物(きゅうりのぬか漬け1本):約2.0g
主食自体にはほとんど塩分は含まれていませんが、麺類のスープやパンの塩分は意外と多いです。味付けの濃いおかずや漬物も塩分が高めなので、食べる量や組み合わせに気をつけることが大切です。
1日の塩分摂取量に関するよくある質問

塩分の摂取量について、よくある質問は以下のとおりです。
- 塩分摂取量の管理方法は?
- 外食で塩分量をコントロールするコツは?
塩分摂取量の管理方法は?
1日の塩分摂取量を適切に管理するには、食品に含まれる塩分量を把握し、調味料や加工食品の使用を工夫することが重要です。
塩分摂取量を管理する主な方法は以下のとおりです。
- 食品表示を確認する
- 減塩調味料を活用する
- 出汁や香辛料を活かす
- 加工食品の摂取を控える
毎日の食事で塩分の摂りすぎに気をつけながら、無理なく続けられる方法を取り入れることが大切です。
外食で塩分量をコントロールするコツは?

外食は味付けが濃く、気づかないうちに塩分を摂りすぎてしまうことがあります。塩分を抑えつつ、美味しく食事を楽しむために、以下の工夫を意識すると効果的です。
- スープや汁物は残す
- ドレッシングやタレは別添えに
- 減塩メニューを選ぶ
- 塩分の少ない食材を選ぶ
- 卓上調味料は控えめに

少しの工夫で、外食でも塩分を抑えながら食事を楽しむことができますね。
1日の塩分量を意識して、健康的な食生活を続けよう

塩分の摂取量を適切に管理することは、健康維持や高血圧・生活習慣病の予防に重要です。日々の食事で、無理なく減塩を続けるために、以下のポイントを意識しましょう。
- 1日の塩分摂取量の目安を把握する
- 減塩調味料を活用し、味付けを工夫する
- カリウムや食物繊維を多く含む食品を取り入れる
- 加工食品やインスタント食品の摂取を控える
- 外食時はスープを残したり、ドレッシングを別添えにする
日々の工夫で 塩分を抑えながら、美味しく健康的な食生活を続けましょう。
「オイシックス」は、厳選された食材やミールキットを自宅に届ける、年会費・会員費無料の食品宅配サービスです。
毎週1500種類以上の安心・安全な商品が揃い、生産者が自分の子どもにも安心して食べさせられる品質です。
15分程度で調理ができるミールキットや、1週間分の食材とレシピがセットになったコースもあり、健康と美味しさを両立させた便利な食事を簡単に楽しめます。
オイシックス以外のサービスが知りたい方はこちらの記事もチェック!
»子育て中の共働き夫婦におすすめの食材宅配を徹底比較!【失敗しない選び方を解説】
»子育て中の共働き夫婦におすすめな野菜宅配ランキング5選【失敗しない選び方を伝授】